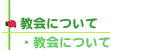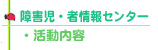(前週よりのつづき)
この「基地付き」は、当時も、今も、その実態は、沖縄では何一つ変っていません。
10月17日の沖縄タイムスの「米軍車両事故328件、日本政府1億円超賠償」も「基地付き」の沖縄で起こっていることへの、日本・日本政府の対応です。「島内で発生した米軍関係者による公務中の車両事故が、2020~24年度の5年間で328件に上ることが、16日、分かった。件数は防衛省が把握している分で、実態はさらに多い可能性もある。これら事故に伴う賠償額として、日本政府は日米地位協定などに基づき、1億円超を被害者に支払った。
「四つの日米密約」(2025年10月6日、朝日新聞)が明らかにする「核抜き」「基地付き」の本土復興は、その時も、それからも、今も、沖縄の人たちの、日常を「侵害」し続けています。「本土」では起こりにくい、理解しようともしない、沖縄の現実です。
・10月22日 「あす嘉手納米軍降下訓練、県、中止求める」
・10月24日 「道路法違反疑い、23歳米兵を逮捕、沖縄署、飲酒検査拒否」
・10月25日 「豪軍C17輸送機、嘉手納基地飛来、哨戒機回収か」
・10月26日 「F35B4機が嘉手納に飛来、岩国基地から」
・10月26日 「軍港移設見直し要求、アセスでシンポ、知事に提言へ」
・10月27日 「建造物侵入疑い、20歳米兵を逮捕、うるま、マンション敷地」
・10月29日 「米の空中指揮機、嘉手納基地飛来、大統領機に随行か」
・10月30日 「米軍嘉手納基地、F35A緊急着陸、暫定配備中、原因は不明」
・10月31日 「米兵性犯罪続出に抗議、市民団体が東京要請」
・11月 5日 「衣類万引き疑い、米兵3人摘発、沖縄署」
・11月 6日 「F35A普天間に飛来、8機、宜野湾市上大謝名(うえおおじゃな)112.7デシベル確認」
・11月 7日 「普天間騒音苦情相次ぐ、米軍4~6日、宜野湾市に日85件、夜間にも100デシベル超」
「宜野湾市の米軍普天間飛行場で、4~6日、哨戒機やヘリの離着陸が相次ぎ、死には苦情が多数寄せられた。5日は、日米合意の航空機騒音規制措置(騒音防止協定)で、規制される午後10時以降も、米軍機の飛行で、100デシベルを超える騒音が確認されており、この日だけで85件の苦情があった」
・10月 8日 「酒気帯びでひき逃げ、那覇署、容疑の米兵、書類送検」
・10月 9日 「米軍刑法犯最多に、県内過去20年で、9月末すでに77件」
(次週につづく)
 [バックナンバーを表示する]
[バックナンバーを表示する]