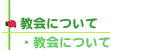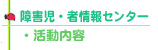前週よりのつづき)
「エネ計画」の「使用済み核燃料の処理(とその再利用)は、日本国内では、その再処理工場の稼働は、延期を繰り返して見通しが立たず、別に建設された乾式貯蔵施設への搬出も始まっています。それでも間に合わなくて、関西電力は原発敷地内にある使用済み核燃料を、稼働の見通しの ない日本原燃の再処理工場へ搬出しようとしています。
「…関電は…2028年度から日本原燃の再処理工場(青森県六ケ所村)へ燃料計198トンを搬出する計画を示した」。もちろんそこでの再処理の見通しは、何一つ立ってはいないにもかかわらずです。その関電では、別に大飯原発敷地内での「乾式保存」を目的とした予定地の地盤調査が実施されています。「…予定地のうち一カ所は山を切り崩して整地した海抜88メートルにあり、周辺斜面が崩れて容器が破損したり、埋もれたりする危険性がないか議論されている」(2月4日、福島民報、山岡耕春、規制委)。
こんな具合に、再処理の見通しは立たず、結局は日本国内ではただただ増やすことになる乾式貯蔵が主流になりつつあります。
他方、日本が再処理を委託しているイギリスでは、再処理から、「地中に埋めて廃棄する方針」が発表されています。
新しい国の「エネルギー基本計画(エネ計画)」では、中でも東電福島の事故を踏まえ、原発をめぐって「依存度を可能な限り低減する」だったのが、「原発回帰」にかじを切り返します。
東電福島の事故の現実、一方で「脱炭素」であるとすれば、再生可能エネルギーと電力需要を減らす以外あり得ないのですが、結局はそして依然として電力は使い放題なのです。
「…原発回帰にかじを切ったのは、これまで減るとしていた電力需要が半導体工場やデータセンターの建設に伴い、2040年度にはいまの約1.2倍に増えると想定したからだ。脱炭素を実現しながら需要を賄うためには、再エネとともに原発が欠かせないとする」。
という訳で、「エネ計画」では「エネルギー安全保障、脱炭素効果が高く最大活用が不可欠」とし、しかし一方で「安全性やバックエンド(放射性廃棄物の処理など)の進捗に懸念の声」は、無視できません。(以上、2月19日、朝日新聞)。
東電福島の放射性廃棄物、中でもその「一部」、事故の「収束」の名のもとに、福島を中心に、広く降り注いだ放射性物質と除染した「除染土壌」は、結局は福島県内、結局は中でも事故の原発が立地する、双葉・大熊両町の「中間貯蔵施設」に運び込まれました。その量はおよそ1400万立方メートル。「中間」を理由に、「世間」を納得させかつ、双葉・大熊両町に了解を取り付ける為には、「最終(処分地)」は必要で、それを「30年」と約束しました。2015年から中間貯蔵施設への搬入が始まっていますから、約束の30年、2045年までの10年が既に経過しています。
最終処分完了の約束は、2045年です。
元々が、放射性物質に汚染された、「処理不能」の汚染物質・土壌ですから、最終処分、最終処分地はどんな意味でも、求めにくいし、受け入れにくいのです。敢えて、そんなものに手をあげる人はいませんから、一方で、おびただしい量の汚染物質・土壌を「除染」を理由に発生させてしまったのですから、「仮置き」から最終処分までは、「中間貯蔵施設」に中間的に移されることになりました。
それが10年経って、「30年後」の約束の残りが20年です。その10年でもちろん何一つ最終らしきものは見えてきませんでした。
しかし、「約束」は約束ですから、環境省によって示されたのが、県外(福島)最終処分に向けての「工程案」です。
(次週につづく)
 [バックナンバーを表示する]
[バックナンバーを表示する]