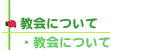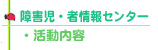(前週よりのつづき)
最終処分場が得られず、しかし、中間貯蔵の約束の期間は、いたずらに月日が過ぎるのを待つよりしかなくて、登場してきたのが、「除染土壌」の「再利用」です。危険だから、除去、除染され、危険だから別の場所に移され、その場所も危険だから「最終」ではなく「中間」になって、当然、その「最終」が得られなくて、いたずらに月日が過ぎるのを待っている訳にはいかないから「再利用」が浮上してきたという訳です。もちろん、その「再利用」にも、誰もどこも手を挙げない結果、手を挙げたのが、事故の東電福島が立地し、言ってみれば消去法でいくと、そこしかなくて決まったのが、双葉、大熊の「中間貯蔵施設」です。
そして、その汚染土壌などの地域での再利用を、率先して手を挙げたのが、双葉町の町長です。
・2月19日 「浪江の特定居住区域、住民帰還」への230ヘクタール追加「『帰還意向あり』15.3%、復興拠点外496世帯」
・2月21日 「分析中デブリ初公開、原子力機構、茨城の研究施設」「放射線防護の項目整理、除染土再利用ガイドライン案で環境省」
・2月25日 「除染土の町内再利用、双葉町長『可能性ある』理解構成必要と私見」
・2月26日 「除染土再利用、双葉町長私見、環境相、危機感を深く受け止める」
・2月27日 「環境相、除染土処分でガイドラン、本県を除く東北関東7県分」「除染土8千ベクレル基準、国審議会か『妥当』。「イノシシ17等、基準超、県放射性物質除去」。
東電福島の事故の後、「事故の終息」「廃炉」への道筋が描かれる中で、いくつかの具体的な問題、課題の処理が必要となりますが、その一つが、避難している人たちが元の住居に戻るために実施された除染です。
途方もない人手と費用で実施された除染で発生することになったのが「除染土」です。
その除染土のことが取り上げられているのが、2月13日の「除染土壌最終処分地/決定時期明示せず」の福島民報、2月25日の「除染土の再利用に一石、『まず福島で』の町長の危機感」の朝日新聞です。
このいずれの新聞記事でも、言わば「注意深く」問題となっている土の定義とされているのが「除染土」あることです。確かに、除染土であることは間違いありませんが、正確ではありません。
東電福島の事故の後(いいえ現在も)、おびただしい量の放射性物質が、環境中に放出されることになり、福島を中心に広い地域が放射性物質で「汚染」されることになり、「途方もない人手と費用」でそれを「拭ったり」「削り取ったり」することになります。避難している人たちが、元の場所、住居に戻るためです。
それによって、避難を余儀なくされた時点の3段階に区分された放射性物質の値を下げる為でした。
避難解除準備区域 1~20m㏜/年
居住制限区域 20~50m㏜/年
帰還困難区域 50m㏜/年以上
これは、「値を下げる」「そして避難解除」のはずでしたが、一回の除染で「解除」にすり替えられて行きました。
そして、その為に実施した除染によって発生した「ものたち」が言われているところの「除染土」です。しかし、「ものたち」は、拭った時に使われたおびただしい量の道具類「防護服」「雑巾」も含まれますから、「除染土」だけではありません。
もう一つ、言い方として不正確と言うか、事実に反するのは、一般的に「除染土」ではなく、いろんな濃度の放射性物質の毒を含む汚染物質であることです。更に、この「汚染物質」がやっかいなのは、含まれている放射性物質は、その毒をどんな意味でも除去したり、中和したりできない正真正銘の「毒」であることです。
ですから、除染した汚染物質は、拭ったり、削ったりした後、一時的に拭ったり削ったりした場所近くに一時保管されることがありましたが、どこか、最終的に保管される場所に移す必要がありました。
しかし、そんな毒物、危ないものを、保管する場所、「最終処分場」は見つかりそうにありませんでした。ここで、一般に保管場所ではなく「最終処分場」と言われたりするのは、この「除染土」「汚染された土壌」などは、含まれているのが放射性物質である為、ほぼ人間的な時間で言えば、そのまま半永久的に保管する場所にならざるを得ない為に「最終」というよりない表現が使われることになっています。
(次週につづく)
 [バックナンバーを表示する]
[バックナンバーを表示する]