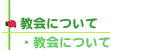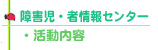(前週よりのつづき)
もちろん、そんな危ないものを、いついつまでも預かって保管する場所、引き受ける場所は得られないし、拭ったり削ったりしたものの、その近くの場所に置くこともできませんでしたから、とにかく一時的に置くという条件で、そのことを明示する呼称として使われることになったのが「中間貯蔵施設」です。
「中間」ですから、当然「最終」もなければならないはずですが、最終の見通しが全く立たない「中間」で、実施されたおびただしい量の「汚染物質」が運び込まれることになったのが、「中間貯蔵施設」です。
もちろん、最終の見通しのない「中間」を引き受ける場所は見つかりませんから、「消去法」で残され、中間貯蔵施設を引き受けることになったのが、事故の原発が立地する、大熊町と双葉町です。
大熊町・双葉町が中間貯蔵施設を引き受けることを、「消去法」としましたが、どんな意味でも、処理不能の「汚染物質・放射能の毒」を、見通しもなく新たに引き受ける場所が現れることは考えにくかったのです。で、既に、「汚染物質・放射能の毒」で、町の多くが帰還困難区域となっている、大熊町・双葉町が、「消去法」で残ることになりました。
しかし、消去法とは言え、そこから最終処分場への移動、「最終処分」は、搬入が始まった2015年から30年の約束でしたが、もちろんどこからも引き受けるという声はあがらないままです。
で、最終処分ではなく、およそ1400万立方メートルの除染土・汚染土を処理したとされる分の「再生利用」に、中間貯蔵施設の双葉町伊沢史朗町長が名乗りをあげることになりました。
双葉町は、東電福島の事故の前の町民・居住者は約7000人でしたが、2025年1月末現在の居住者は181人です。それも、避難していた町民が帰還した結果の181人ではなく、およそ60%は「移住者」と言われています。大地震・大津波そして東電福島の事故からおよそ14年、町に戻った、いいえ戻れた人は、事故前の約7000人に対して、移住者を差し引けばおよそ70~80人ということになります。残念ながら「町の体」をなしていないのです。
それは、そもそもが戻りにくい帰還困難区域であり、かつ最終処分の見通しの立たない、中間貯蔵施設の故に戻れない町双葉町だからです。
そんな町の町長が「除染土の再利用に一石」ということで、再生利用の意向を表明することになったのです。
「福島第一、第二原発のエネルギーを使っている首都圏の皆さんの理解が進んでいない危機的な状況を考えた」
「福島で利用しないのに、なぜ首都圏が受け入れるのか」という声も聞き、「『そうだな』と思った。首都圏の理解を進めるには、まず福島県内で取り組む必要がある」
この意向表明に、無理があるというか、どんな意味でも必然性が見つかりにくいのは、もともとが「消去法」で、中間貯蔵施設を引き受けさせる、正確には押し付けることになったことへの、たとえば「首都圏」と言われている人たちの、最低限の道義的責任が一切問われていないことです。
別に、同じ「消去法」とは言え、中間貯蔵施設を引き受けることになった大熊町の町長は、この問題の責任の所在について、「控えめ」に指摘しています。
「大熊町の吉田淳町長は『除染土は国の問題。町がどうこう言えない』と語った」。
(次週につづく)
 [バックナンバーを表示する]
[バックナンバーを表示する]