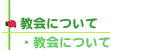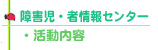(前週よりのつづき)
「除染土の再利用に一石」と意見が表明されたりする、東京電力福島第一原発事故に伴う除染で出た土壌の「再利用」と「最終的に埋め立て処分する場合」の「基準案」が2024年9月17日に、環境省によって公表されていました。
「再利用の際は放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8千ベクレル以下の土壌を使用する。
「埋め立て処分」の際には基本的に遮水シートなどの地下水汚染防止対策を不要とするなどと明記する。
こうした除染土壌の「再利用基準案」と「埋め立て処分案」が公表されるのは、以下のような「放射線防護の基本的な考え方」に基づいているとされます。
「…周辺住民ら一般公衆の追加被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにする。使用する土壌の放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8千ベクレル以下の基準は、最も被曝すると想定される作業者などで再生利用の土壌を扱った際、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト未満になるよう設けた。放射性セシウム濃度が8千ベクレルであれば、作業者の追加被ばく線量は年間0.93ミリシーベルトに抑えられるとの試算結果に基づいている」(2024年9月18日、福島民報)。
こうした「再生利用」「埋め立て処分」の基準案で「科学的に安全性が担保」されるのであれば、「再生利用や最終処分に向けた国民の理解」、福島県が求めている「県外処分」、「除染土壌の県外最終処分」が具体化するだろう、ということなのです。
でも、そうして、「除染土壌」についての「放射線防護」の基本的な考え方が示し得るのであれば、まずは、「除染で出た土壌」の「中間貯蔵施設」のある双葉町が名乗り出てもおかしくはない、ということで名乗り出たのが双葉町の伊沢町長です。
たぶん、既に現在中間貯蔵されているのが除染土壌であってみれば、むしろ誰より早く名乗り出ることで、他の地域・人たちも名乗り出やすいということなのでしょうが、何か少なからずと言うか、大幅にずれているように思えます。
更に、「最も被ばくすると想定される作業者が公共事業などで再生利用の土壌を扱った際、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト未満になるよう設けた」とありますが、その東電の事故で避難となった地域・人の被ばく線量の基準とはかなりかけ離れているのは、なぜだろうか。
こうして、東電の事故のその後で、中でも放射性物質が降り注ぐことになった地域の、線量の基準は、繰り返し言及してきたように、以下のようになっています。
(次週につづく)
 [バックナンバーを表示する]
[バックナンバーを表示する]