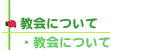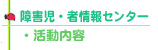(前週よりのつづき)
更に、その中間貯蔵施設への「使用済み燃料の搬出方針」が、東電福島第一原発5,6号機、第二原発からも搬出の方針が示されています。
「東京電力は、福島第一原発5,6号機と、第二原発1~4号機で貯蔵している使用済み核燃料の一部を青森県むつ市にある国内唯一の使用済み燃料中間貯蔵施設へ搬出する方針を示した」。(7月8日、福島民報)。
で、その「中間貯蔵施設」は、次のような具合で、既に、東電柏崎原発の使用済み燃料の「受け入れ」を始めています。
「…むつ市の中間貯蔵施設は健全な使用済み核燃料を金属製容器に入れ、自然風で冷やす『乾式貯蔵』を原発敷地外で行う国内唯一の施設。東電と日本原子力発電(原電)が共同出資で設立したリサイクル燃料株式会社が運営し、東電と原電の原発から出た使用済み核燃料を六ヶ所村の工場で再処理するまでの間、最大50年間保管する。昨年9月に東電柏崎刈羽原発(新潟県)の使用済み核燃料69本を国内で初めて受け入れた」。
原子力発電を行うにあたって、現在の科学では先に進めることのできない「処理不能」の現実を、「言葉の定義」によって、あたかも可能、あり得るとしてしまう言葉がいくつもいくつもあります。
この7月8日の福島民報の引用の中にも、それが頻発・繰り返されています。
(1)「中間貯蔵施設」
(2)「健全な使用済み核燃料」
(3)「自然風で冷やす『乾式貯蔵』」
(4)「…リサイクル燃料貯蔵」
(5)「…使用済み核燃料を六ヶ所村の工場で再処理する」
この(1)~(5)は、「処理不能」の放射性廃棄物問題のほんの一部であり、他のすべてのことは、核燃料サイクルの難しさ、困難さをある意味で立証しています。
原子力発電所の稼働が、他の施設と異なっているのは、核反応によって発生する厖大なエネルギーとは別の、放射性物質が、一つにはそれに「被ばく」した場合の人体への影響が大きいこと、及びその処理が技術的に難しいことなどです。
たとえば、放射性物質・放射線は被ばくした場合、その性質及びエネルギーは、人間の生物としてのエネルギーに対して、ケタ違いに大きく、致死量は7シーベルトと言われており、東海村臨界事故の大内さんたちは、被ばくにより体のすべての細胞が破壊されて亡くなっています。
そして、その放射性物質を処理する技術も確立されていません。と言うか、困難なのが、放射性物質です。
ですから、東電福島の重大事故で、環境中に放出された放射性物質は、施設を設置するにあたってのそれなりに高度な「技術」とは別に、その処理は、言わば「人海戦術」で削ったり拭ったりの「手作業」で実施するよりありませんし、その結果集められた「汚染物質」は、最終処分されることなく、汚染されたまま「保管」するよりありませんでした。それが言うところの「中間貯蔵施設」です。
これらのことは、原子力発電所を稼働させようとする時から、解り切ったことであって、たとえば、一旦は使用した燃料の「使用済み核燃料」の場合も、そのまま「使用済み」とはならないで、高濃度に汚染された放射性物質として残ってしまいます。
と言うことは、解り切っているのに、原子力発電所を稼働させ、使用済み核燃料が発生し続けるのに、敢えてそれを稼働させるには、それを再利用するという「物語」が作られていたからです。
「核燃料サイクル」です。
(次週につづく)
 [バックナンバーを表示する]
[バックナンバーを表示する]