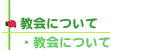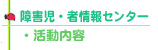(前週よりのつづき)
そうして「多岐」に及ばざるを得ないのは、原子力発電所によって「電力」を生み出す事が、一方で必然的に処理不能の放射性物質を環境中に生み出す「科学・技術」でもあるからです。
中間貯蔵して、最終処理する(処理場に移す)ことになっている除染土は、最終のない中間貯蔵でしたから、「福島県外での最終処分」の約束は、見通しは立っていません。
見通しが立たないところで、「再生利用」が浮上し、「除染土利用、全国に拡大、政府工程表、国の出先、民間にも」となってきました。(8月27日、朝日新聞)。
除染土の「県外最終処分」は、中間貯蔵施設への搬入(2015年)から30年の約束で、その期限は2045年です。もちろん、最終が見つからない為、事故の原発に最も近い、大熊・双葉町に決まりました。「処分にまわす土を減らすため、放射性物質の濃度が1キロあたり8千ベクレル以下の土を公共事業などに使う」のを「再利用」としてきました。
その再利用を含めた、除染土対策の「工程表」の中で、再生利用が明示されています。
「工程表では、再生利用に使える土は、『資源』だと強調。今年7月に、東京・永田町の首相官邸の庭に埋めた例に続き、霞が関の中央省庁でも9月から順次、花壇などに使う。今後5年間で、全国にある政府の出先機関や所轄法人、民間企業が行う土地造成などにも生成利用先を広げる」(8月27日、朝日新聞)。
この場合、「放射性物質の濃度が1キロあたり8千ベクレル以下」を、「再利用する」ことになってしまい、それの実施の一歩が「首相官邸の庭」だったりするのは、結果的には重大事故で、それを環境中に放出させてしまった「科学・技術」が、「人間は生きものであり、自然の一部である」という、生きものの世界の理解が成り立っていなかったことを意味します。
(次週につづく)
 [バックナンバーを表示する]
[バックナンバーを表示する]